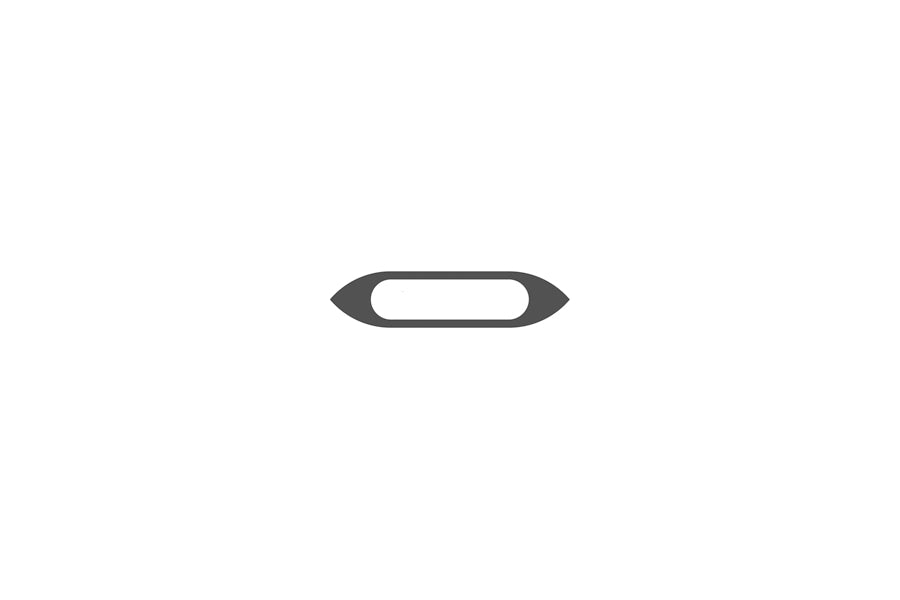2012年7月25日、群馬県安中市にある「碓氷(うすい)製糸工場」を見学に訪れました。 銀座もとじでも、雄の繭だけから取れる極上の絹糸「プラチナボーイ」の器械製糸をお願いしている製糸工場です。


蚕の飼育は、大きく分けて年4回、春蚕(はるご:5月掃き立て)、夏蚕(なつご:6月掃き立て)、初秋蚕(しょしゅうさん:7月掃き立て)、晩秋蚕(ばんしゅうさん:8月掃き立て)と季節ごとに行われます。
(1)検査
全国各地から届いた袋詰めの生繭は、「荷受け場」に届き、そこで蚕品種ごとに品質管理のためのサンプリングを行い、選除繭(せんじょけん)といって汚れなどの欠点のある繭の割合を調べるなど、品質の確認を行います。
(2)乾繭
その後、「乾繭(かんけん)」といって、繭に熱風を当てて、蛹を殺し、乾燥させる工程へと移ります。繭を金網のコンベアーに載せて、30分かけてゆっくりと乾燥機の中を流れていき、最高125度程度で上の段、その後下の段に落ちて、約60度での乾燥を30分間。それを、5〜6時間かけ、5往復して乾繭が完了します。


蛹は、新潟県小千谷の錦鯉のエサ、釣りの練エサ、長野県伊那の蛹の佃煮などの食用として利用されます。
乾繭を終えた繭は、その後、倉庫へと移動し、品種、季節(何年、春、夏、秋など)、生産地域で分けて、保管されます。
(3)選繭(せんけん)
乾繭を終えた繭を「選繭台」に乗せて、下から光を当てて透かしつつ、汚れた繭をひとつひとつ手で取り除いていく作業を行います。通常の繭よりひとまわり大きめの玉繭(二頭の蚕が一緒にひとつの繭を作ったもの)はよけて、紬用などのために別に集めます。

(4)煮繭(しゃけん)

繭を生糸にする際には、次に煮繭をします。水に沈むように重曹を入れて約20分間、煮繭機にかけて煮ます。繭を煮て柔らかくすることで、繭糸を層状に固着させている膠(にかわ)状のセリシンというタンパク質を膨潤軟化さて、糸をほぐして取り出しやすくします。
 糸口が出てくるまでの繭は、生糸として製糸はされず、くず糸として取り除きます。それらをまとめて乾燥させた物が、「生皮芋(きびそ)」(写真右側)または、生皮芋糸となって、生糸とは別の用途に使われます。現在それらは、パウダー状にして食品に入れたり、シルクプロテインとして化粧水に入れたりして利用されています。
糸を取り続けて繭層が極めて薄くなった内側のほうも、最後までは生糸としては使えず、くず糸となります。その繭層の内側のくず糸は、「比須(びす)」(写真左側)と呼ばれます。薄皮繭から蛹をとった部分です。内側のくず糸は、絹の靴下や、シルクニットなどに使われています。
糸口が出てくるまでの繭は、生糸として製糸はされず、くず糸として取り除きます。それらをまとめて乾燥させた物が、「生皮芋(きびそ)」(写真右側)または、生皮芋糸となって、生糸とは別の用途に使われます。現在それらは、パウダー状にして食品に入れたり、シルクプロテインとして化粧水に入れたりして利用されています。
糸を取り続けて繭層が極めて薄くなった内側のほうも、最後までは生糸としては使えず、くず糸となります。その繭層の内側のくず糸は、「比須(びす)」(写真左側)と呼ばれます。薄皮繭から蛹をとった部分です。内側のくず糸は、絹の靴下や、シルクニットなどに使われています。
 (5)繰糸(そうし)
(5)繰糸(そうし)

ここからは、製糸工場における製糸の工程の要となる「繰糸」の工程に入ります。
繭の糸口を見つけ、繭糸を引き出し、目的の太さ(繭ひとつから引き出される糸の太さは、約3デニール。21デニールの糸を製糸する場合、
 糸口を見つけられた繭は、繰糸槽の周りをぐるりと周っていく小箱のようなコンベアーに移り、そこから均一な太さの生糸となって、上部にある小枠に巻き取られ、繰糸されていきますが、この繰糸器では、小箱のコンベアーから小枠に繰糸される際に、主な2つの装置を経て行きます。
糸口を見つけられた繭は、繰糸槽の周りをぐるりと周っていく小箱のようなコンベアーに移り、そこから均一な太さの生糸となって、上部にある小枠に巻き取られ、繰糸されていきますが、この繰糸器では、小箱のコンベアーから小枠に繰糸される際に、主な2つの装置を経て行きます。
ひとつは、繭糸が1本にまとまって上に繰り上がって行く際に糸の太さを感知する「集緒器(しゅうちょき)」という小さな白いボタンのような、真ん中に糸の太さに合わせた穴のあいた装置。大きさは親指大で、陶器やセラミックでできており、0.2〜0.4mmほどの直径の穴が空いており、生糸の太さを調節します。
もうひとつは、糸の太さをチェックし、汚れを取り除く「繊度感知器(せんどかんちき)」(写真下部、赤枠)。製糸に適さない糸は、繊度感知器についた2枚のガラス盤が摩擦力によってそれを感知します。


(6)揚返し(あげかえし)
自動操糸機で繰糸された生糸は、上部にある小枠に巻き取られます。小枠に巻き取られた状態の生糸を、別の器械で大枠に巻き直す工程が「揚返し」です。この後、梱包する際に取り扱いやすいように一定の大きさと量の束にしますが、生糸は「綛(かせ)」という単位で扱われており、小枠から大枠に巻き取られたものが、一綛(ひとかせ)として束ねられます。
(7)仕上げ・出荷
大枠からはずし、ほどけないように糸留めして、綛(かせ)という単位で束ねたり、大枠ではなくプラスチック製のボビンに巻き取り(チ−ズ巻※)、出荷に便利なかたちにします。綛の一束を、4列6段の計24綛に束ねたものを「一括(いっかつ)」といいます。”一括払い”などの一括の語源ですね。綛の重さは約208g、24綛をまとめて束にした一括は、約5kgです。

 名古屋帯
名古屋帯
 袋帯
袋帯
 紬・綿・自然布
紬・綿・自然布
 小紋・江戸小紋
小紋・江戸小紋
 訪問着・付下げ・色無地ほか
訪問着・付下げ・色無地ほか
 浴衣・半巾帯
浴衣・半巾帯
 羽織・コート
羽織・コート
 肌着
肌着
 小物
小物
 履物
履物
 書籍
書籍
 長襦袢
長襦袢
 小物
小物
 帯
帯
 お召
お召
 小紋・江戸小紋
小紋・江戸小紋
 紬・綿・自然布
紬・綿・自然布
 袴
袴
 長襦袢
長襦袢
 浴衣
浴衣
 羽織・コート
羽織・コート
 額裏
額裏
 肌着
肌着
 履物
履物
 紋付
紋付
 書籍
書籍