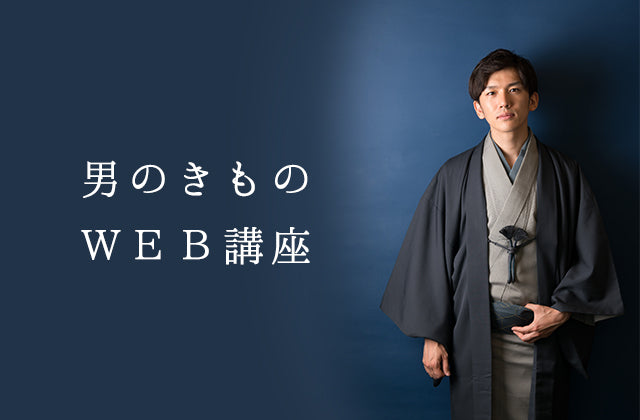着物から見えてくる日本
そもそも、正装・礼装とは、単にフォーマルな装いであるというだけでなく、礼を尽くす心を表すために着用するものでもありますから、精神面への影響も決して無視はできません。衣服を改めるという行為によって「私はあなたのことを大切に思っています」という、自らの思いを相手に伝えているわけです。 また同時に、普段着とは違う晴れ着に身を包むことで、そうした厳粛な気持ちを改めて自分自身に言い聞かせる意味も込められています。だからこそ、日本人は古くからハレとケの世界を分けて考え、これらを混同しないことで良識ある精神を維持しようとしてきたのです。 「襟を正す」「褌を締めなおす」という言葉も、それぞれ気持ちを引き締めることを意味しますが、これらも和服ならではの仕草から出た言葉です。こうした言葉の意味からも、衣服を改めるという行為には、精神的な深い意味が込められていることが窺えます。 ところで、一口に正装・礼装と言っても、和装にはさまざまな服装があります。男性の場合は、黒紋付羽織袴が第一礼装とされていますが、これは現在の民間和装においての話です。庶民の男子の礼装を羽織袴としたのは江戸時代の天保以降のことで、男性の第一礼装を黒紋付羽織袴と定めたのは、実は明治になってからのことなのです。これについては、次のようなエピソードが語られています。 明治以降、洋風の文化が日本に入って来て、日本人も西洋式の公式なパーティに出席する機会が増えましたが、そうした場で何を着るべきかが問題となりました。洋装にはモーニングやタキシードといった「礼服」が当然のようにあったのに、和装の場合は、それまで公家や武家、町人といった集団毎に風習が異なっていたため、対応する特定の服がなかったのです。このため、外国の礼服に合わせて日本の礼服を無理矢理一つに統一してしまったというのが実態のようです。 その結果、西洋のブラックフォーマルに対応して、男女とも黒紋付の紋服が最も近い衣服として選ばれ、それに合わせる男性の袴に、あのフロックやモーニングに合わせるストライプのズボンに似ていた、仙台平と呼ばれる上等な織りの袴を合わせたわけです。 非常に現実的な事情から定着した組み合わせでしたが、デザイン的にも秀逸であり、結果的には素晴らしいスタイルだと思います。実際、紋付袴を身に着けると、不思議と緊張感が漂い、背筋が伸びる思いがするものです。 日本人は昔から、心意気を大切にした庶民の間でも、一番いい着物を「一張羅」として大切に扱い、晴れ着としてどんな場でも利用して来ました。晴れ着というのは、祭り装束の正装に様々なものがあるように、着る人にとっての正装でもあり、必ずしも特定の服装に限るわけではないことを付け加えておきましょう。 今日では、お正月でさえも日常の延長と大差ない感覚に陥りがちですが、いつでも和服に身を包むことで、日本人であることの誇りと自覚を呼び覚ますことができるでしょう。私たちの祖先が遺してくれた知恵と精神を、和装の世界からもぜひ感じてみて下さい。男のきもの WEB講座 一覧
 名古屋帯
名古屋帯
 袋帯
袋帯
 紬・綿・自然布
紬・綿・自然布
 小紋・江戸小紋
小紋・江戸小紋
 訪問着・付下げ・色無地ほか
訪問着・付下げ・色無地ほか
 浴衣・半巾帯
浴衣・半巾帯
 羽織・コート
羽織・コート
 肌着
肌着
 小物
小物
 履物
履物
 書籍
書籍
 長襦袢
長襦袢
 小物
小物
 帯
帯
 お召
お召
 小紋・江戸小紋
小紋・江戸小紋
 紬・綿・自然布
紬・綿・自然布
 袴
袴
 長襦袢
長襦袢
 浴衣
浴衣
 羽織・コート
羽織・コート
 額裏
額裏
 肌着
肌着
 履物
履物
 紋付
紋付
 書籍
書籍