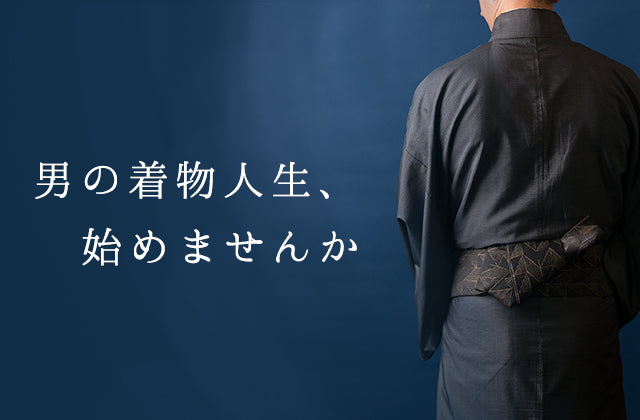浴衣には下駄
男物の履き物の中でも、カジュアルに利用されるのは下駄で、特に浴衣に合わせる履き物です。格上の着物には合わせられませんが、同じ着流しのスタイルでも、履き物を草履から下駄に替えただけで、ぐっと砕けた印象になります。雨の日には「雨下駄」
ただし、雨のときだけは着物の格とは関係なく、雨下駄を履きます。雨下駄は、普通の下駄よりも歯が薄めで高くなっており、爪皮つまがわと呼ばれるカバーが付いています。爪皮は、爪先部分にだけかぶせる革やビニール製のもので、付属のゴムを歯の部分に引っ掛けて使います。下駄の形
下駄は皆同じ形のように思っていらっしゃる方が多いかも知れませんが、実は、微妙に形が違っています。最も一般的な下駄は、「大角だいかく」と呼ばれるもので、大きくて四角く、歯が2枚付いています。 また、関東では「のめり」あるいは「千両」、関西では「神戸」と言われるものがあります。これは前の歯が、横から見ると爪先の方へ斜めになっているものです。 ほかに、「右近(うこん)」と呼ばれるものがあり、これは底が舟形で真ん中に切れ込みが入っており、緩いカーブがついています。爪先が上がっているのも特徴です。裏がサンダルのようにゴム貼りなので歩きやすく、足が疲れることもありません。初心者におすすめと言えるでしょう。また、下駄の幅は細めのほうが、すっきりと息に見えます。下駄の素材
素材については、桐の白木ものに人気があります。一枚板から作られたものは、柾目(まさめ)がしっかり通っていて、これが本物です。 白木のほかには、焼いて磨き、木目を際立たせたものや、漆(うるし)塗りのもの、鎌倉彫のもの、さらに、表に畳や竹などを貼ったものもあります。鼻緒
鼻緒は黒の布地が一般的ですが、紺や茶、グレーなどの色物もありますし、革のものもあります。下駄は素足で履くことが多いので、自分の足に合わせて鼻緒をすげてもらうことをおすすめします。男の着物人生、始めませんか 一覧
 名古屋帯
名古屋帯
 袋帯
袋帯
 紬・綿・自然布
紬・綿・自然布
 小紋・江戸小紋
小紋・江戸小紋
 訪問着・付下げ・色無地ほか
訪問着・付下げ・色無地ほか
 浴衣・半巾帯
浴衣・半巾帯
 羽織・コート
羽織・コート
 肌着
肌着
 小物
小物
 履物
履物
 書籍
書籍
 長襦袢
長襦袢
 小物
小物
 帯
帯
 お召
お召
 小紋・江戸小紋
小紋・江戸小紋
 紬・綿・自然布
紬・綿・自然布
 袴
袴
 長襦袢
長襦袢
 浴衣
浴衣
 羽織・コート
羽織・コート
 額裏
額裏
 肌着
肌着
 履物
履物
 紋付
紋付
 書籍
書籍