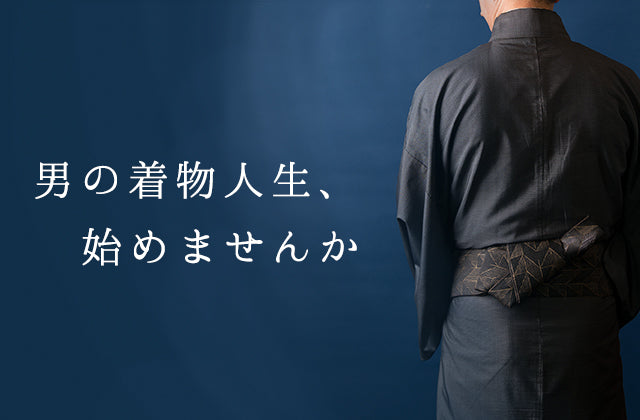大正時代のハイカラファッション
洋装が一般化し始めた大正時代の古い写真を見ますと、着物と洋小物がバランスよく使われていることに気付きます。着物を着ている人がカンカン帽のようなものをかぶっていたり、洋ステッキを手にしていたり・・・。当時、「ハイカラ」と呼ばれた格好です。この写真に写っている人物がまた、とても生き生きしているのが印象的です。ハイカラファッション平成風
時代は流れ、今は洋装が一般的になって、日常生活も洋小物なしでは成り立たなくなっています。ただ、いざ着物に合わせるとなると、使い慣れたはずの洋小物をどう扱っていいか分からなくなりがちです。 しかし、決まりは何もありません。快活としたハイカラな人たちのように、着物と洋小物を自由に組み合わせればいいと、私は思っています。普段、洋装のときにご使用なさっている帽子をかぶってみたり、お手持ちのバッグを合わせてみたり・・・。例えば、シックなものの多い男物のマフラーやスカーフは、あえて和物にするよりも、洋物のほうが着物にしっくりくる気がします。 私のお気に入りは、薄いスカーフを色違いで2枚用意し、くるくると丸めて衿元に当てがう方法です。冬場にはスカーフやマフラーを巻くときには、両端を懐ふところに差し込むようにすると暖かく、着物姿にもぴったり合います。

冬のおしゃれにショールとインバネスコートを合わせて
洋の小物活用術
着物姿のとき、手に持つのは合財袋がっさいぶくろや信玄袋が中心でした。合財袋とは「一切がっさい入れる袋」という意味で、幅広い用途に使われていました。しかし、男性でも荷物が多くなった今では、とても入りきらないということがほとんどでしょう。そのような場合、和の袋や巾着などを持たずとも、普段使っていらっしゃるセカンドバッグで十分です。 仕事中も着物姿でいる私は、いつも大荷物ですから、大きな皮製のバッグを抱えて歩いております。これが、不思議に違和感を感じさせません。ヨーロッパのブランドバッグなども、色合いがとてもシックですから、着物によく合います。最近は、女性も着物姿に洋装用のバッグを持つ方が増えていらっしゃいました。和装だから必ず和小物という図式はありません。 手持ちのものをうまく利用しているうちに、次第にどっぷり和に浸った小物にも興味が出てくるかもしれません。和小物をじっくり揃えるのは、着物に十分慣れてからでもけっして遅くないと思います。*合財袋・信玄袋・・・・・ともに、口の部分にひもが通っていて、袋状になっている。信玄袋は、武田信玄の肖像画の背景に描かれている袋物に似ているところから名づけられた。
男の着物人生、始めませんか 一覧
 名古屋帯
名古屋帯
 袋帯
袋帯
 紬・綿・自然布
紬・綿・自然布
 小紋・江戸小紋
小紋・江戸小紋
 訪問着・付下げ・色無地ほか
訪問着・付下げ・色無地ほか
 浴衣・半巾帯
浴衣・半巾帯
 羽織・コート
羽織・コート
 肌着
肌着
 小物
小物
 履物
履物
 書籍
書籍
 長襦袢
長襦袢
 小物
小物
 帯
帯
 お召
お召
 小紋・江戸小紋
小紋・江戸小紋
 紬・綿・自然布
紬・綿・自然布
 袴
袴
 長襦袢
長襦袢
 浴衣
浴衣
 羽織・コート
羽織・コート
 額裏
額裏
 肌着
肌着
 履物
履物
 紋付
紋付
 書籍
書籍